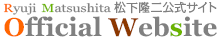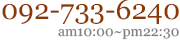先日のブログのなかで ぽろっと書いたひとことに対し ある方からとてつもなく大きな問いを投げて戴いた。長くなるが以下にそのコメントを 全文あらためて掲載させていただく。
===============
【素朴な疑問として…】
ご挨拶失礼します。
コラムの本題からはズレた問いになるのかも知れませんが、素人の素朴な疑問として、一つ質問をさせてください。
>楽譜の音を減らしたり増やしたりアレンジすることにまるで抵抗が無くなってきたが その時点でじぶんが最早《クラシックミュージシャンでない》ことを感じる。
“ほんとうにそうだろうか?そうなのだろうか?…” という問いです。音楽の知識のない者ですので、“えっ!そうなのですかぁ?”というニュアンスの方が真意です。
私の記憶違いかもしれませんが、たとえばクラシック音楽の譜面の右上辺りに「〇〇編」という記載をみたような気もしますし、編曲されたクラシック音楽というのは、それはそれでクラシック音楽として<在る>ように思っておりました。
先日は娘の通う幼稚園の音楽行事がありました。園児が大・小太鼓、カスタネット、トライアングル、ウッドブロック、タンバリンで合奏し、大人がピアノとヴァイオリンで伴奏をつけるように編曲されていました。曲目はドボルザークの「新世界から」でした。
変な言い方になりますが、聴いていた私には「新世界」としてきこえていたのです。(娘は後日オーケストラによる演奏を動画でみて「なにこれ?」と申しました。娘の中では「新世界」は編曲ヴァージョンがスタンダードなのですね)
行事の当日は、編曲者も来賓として来られ、てっきりというか、すっかりというか、編曲された「新世界」ではありますが、その世界にいざなわれた聴衆でした。
たしかに以前 “クラシック音楽は再現芸術だから…云々” と読んだことはあります。松下様の言わんとされることも、おそらくはこの意味かと受け止めております。
どうなのでしょうか?もし、オリジナル曲が編曲され、編曲された音を一音違わずに弾かれればそれは<クラシック音楽>として成立するということでしょうか?
そして、編曲者と奏者が同一人物の場合には<最早クラシック音楽ではない>となるのでしょうか?
また、時代によっても<クラシック音楽>の定義は変わり、編曲(アレンジ)後の曲への認識(評価)が変わり得ないでしょうか?曲や時代によっては、編曲後の曲もまた普遍的な一曲として受け入れられるということはないでしょうか?
あらためて<クラシック音楽>って何だろう?と思わされました。
さて<左手によるピアノ曲>は、ピアニストの舘野泉氏を通して知りました。もともと左手のための曲は第一次世界大戦で右手を失った奏者の存在から生まれたとか。
ならば…とふと思うのです。たとえばですが、すでに高齢社会を迎えている日本ですから、加齢とともに困難をきたし、オリジナル楽譜通りには弾かれなくなった愛好家も実は結構いらっしゃるのではないか?とか。
高齢社会のことはあくまで一例ですが、何かしらの事情によるニーズといいますか、アレンジされた楽譜を待っておられる方もいるのではないかと。
弾きやすく音を減らされたり増やされたりしたとしても愛好家の心のなかでは、<あの曲を弾く喜び>みたいなものは不変で、その人にとっては「月光」は「月光」に変わりなく、それはあのベートヴェンによるまさに<クラシック音楽>なのではないかな?…と、物を知らないだけに思えたりします。
松下様からのご返信をいただいた折にはもちろん感謝です。一方で、幅広く読者の皆さまからもいろいろ伺ってみたい思いもあり、長くなりましたが、あえてコメントへ投稿させていただきました。よろしければお願いいたします。
================
このようなお題を頂戴したのだが なにぶんテーマとして大きく 《わたしのこれまでの経験から思うこと》を今後何回かに分けて書いてゆきたい。これまで書いた内容と重複することも多々あると思うし たぶん成り行き上の脱線も多くなるに違いない。
先に申し上げておくが 今回の問いに対する私の答えは「無い」。ただ脱線やなにげない言葉の枝葉から みなさまのなかでなにかがふくらみ 独自に発展していくものがあったりしたら それだけでうれしい。
2024.06.18.