一月の怒涛の本番ラッシュもひと段落し、ようやくブログへと気持ちが向かいました。あいだが空いてしまってごめんなさい(誰に向かって謝っているのかよくわからん。待っていてくれるひとが居てくれたと仮定しての自意識過剰謝罪です)。
今月は大阪に二度も行くことが出来とっても幸せでした。いつもあたたかく迎えてくださる親友ギタリストの岩崎慎一さん、大阪ギタースクールの井谷正美先生、百合江さん、レッスン会を主催してくださった高橋通康さん、レッスン受講生の皆様、岩崎教室の皆様、コンサートにご来場くださった皆様、裏方スタッフとしてご協力くださった皆様、猪居先生、共演して下さった松崎祐典さん、麻尾佳史さん、本当にありがとうございました~!!!
そうそう、そういえば大阪で岩崎さんから貴重な話をうかがうことが出来ました。前回のブログでネタにしていたラウドネス高崎晃氏の話。学生時代メタル大好き少年だった岩崎さんは高崎氏がクラシックギターを習われた過去についてご存知で、ライヴを観に行ったときに高崎氏がギターソロ・タイムでなんと『禁じられた遊び』をタッピング奏法で全て弾ききったのを目撃したそうな、、、、、ってそれが「クラシックギターをマスターした」成果かいっっ!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「若い人は何を考えてるかわからない、、、、。」
だがそれは単に若い人の意見を聞くチャンスを作れてないだけの話だ。
年長者は若い人がものを言いやすいシチュエーションを設定することこそが大事なのだろう。
自分がその能力に長けてるとは到底思えないが、先日二十代半ばの若い友人ギタリスト、山田賢
さんがうちの教室を訪ねてきた折、こういうことを口にした。
「先生や諸先輩方を見ていると【個人を追いかけてる】ことが多いように見えますが、僕らの
世代は個人というよりは【ジャンルを追いかけている】気がします。」
この意見は山田さんによる「一個人的な見解」ととることも勿論出来る。
だが私にはそう切り捨てるにはもったいな過ぎるほどの重要な示唆を含んでるように思われる
のである。
つまりはネット社会においては『前人未踏の個人技』も『巨匠の熟練技』ももはや権威の衣を
纏うことが不可能な【あまたある情報源のうちのひとつ】でしかないのである。
山田さんのその言葉を聞いたとき軽いショック(というか戸惑い)を覚えたのは、要するに
パコ・デ・ルシア、アンドレス・セゴヴィア、マイルス・デイヴィスなどの個人的能力に憧れを
持ち、追いかけること自体、既に前時代の価値観となってしまってる現実を突きつけられた気が
したのである(もちろん彼はそんなことは一言も言ってないのだが、、、)。
ここでちょっと「個人を追いかける」「ジャンルを追いかける」このふたつの違いについて検討
してみたい。
「個人を追いかける」というとき、その個人のルーツもしくは内面を探っていくことによって
掘り下げが可能であり、世界を広げてゆくことが可能になる。そしてその根っこにあるのは
おそらく『まず個があってそれを社会が取り巻いている』という視点である。
一方「ジャンルを追いかける」というときには、枠を決め、その中をいかにアクティヴに動き
回るかが重要になる。そしてその根っこにあるのはおそらく『まず世の中(社会)があってその
中に個人がある』という視点である。
「ジャンルを追いかける」というのはつまり『わたしはクラシックギターに興味がある。そんで
ネットで調べてみたら、その世界にはJ.ペロワ、M.バルエコ、大萩康司、A.セゴヴィア、
M.ディラ、J.ブリームなど様々いるらしい。』という所から入っていく。これはリサーチする
側にとって、もはや他者の個性(個人技)というものは参考資料的役割しか果たさない、という
ことなのだ。他者に対する「あこがれ」「崇拝」といった感情は極めて薄い。
昭和の私から見るといささか「ドライ」かつ「淡白」だねえ、、、。
でも若い世代から私を見るとなんとも暑苦しいんだろうな、、、。
(つづく)
個性について(その2)
| カテゴリー: |
|---|
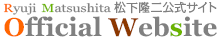

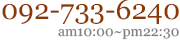
入り方の違いが有るのかも知れませんね。 今の若者が先生のおっしゃるジャンルからスタートして時間経過を考えた時、彼がずっと継続すると仮定した時、数年後、あるいはもっと先に行き着くところは個人かも知れませんね。 そうであるなら先生がおっしゃるように若者とのコミュニケーションはお互いに面白い遭遇、発見の場になるかも知れませんね。 マーケティングの世界では時間軸は大切な要素のひとつでした。
Yoshimoto Takaoさま
含蓄のあるコメントありがとうございます。
「時間軸を逆に動く」のは日常クラシック音楽の演奏にたずさわる人間がやっている行為そのものですね。作曲家が曲を書き始める地点をゼロ、完成した楽譜を100の地点とすると、楽譜を入手し演奏する人は100からゼロに向かってゆく、すなわち作曲家と逆の過程を辿ってゆく事になるわけで、わたしも常にその作品の「ゼロの地点」を渇望しながら演奏しています。
今わたしが個人的に興味あるのは、時間軸を「逆にたどった」事によって起こる【誤差】や【ズレ】についてです。
むかし三善晃さんと高橋悠治さんが対談で「イマジネールの主体は個にあるのか集団にあるのか」で議論白熱し、結局物別れに終わりました。『ジャンルからスタートして個人に行き着いた』際、逆の場合と比べて【誤差】や【ズレ】がいかほどのものなのか、どういう質の違いが出るか、あるいは「全く誤差なくたどり着く」ことが可能なのか、、、興味が尽きないところです。
プロの音楽家は真理を追及する、求道者ですね!!
合唱しか知らないアマの私はゼロ地点など思いもよらないことです。 ただ単にいろんな作曲家の音楽に出会い、喜びや悲しみ、怒りなどを感じて聞いていただく方に訴えるというか共感も求めているのですかね。
しかしゼロ地点とのズレや誤差となると作曲家のゼロ地点が、つまりベンチマークとなるものが分からないといけないということでしょうか。 難しい!
確かに難しいですね(笑)。
自分の演奏を客席で体験してみたい、、、というのと同じぐらいの無理があるかもしれません。
ただこの【ズレ】や【誤差】の存在そのものを冷静に容認しておくことで「客観視」出来ると言うか、独りよがりの演奏から逃れられる確率が高くなるようなそんな気がします。
ワタクシも暑苦しい人間でやんす。ジェネレーションギャップといえばそれまでですが、情報量と情報にアクセスできるスピードの発達に由来するものかもしれませんね。余裕があった(時間がかかった)昔は自分の中で妄想し熟成させる十分な時間もありましたし。そんな自分もある意味すっかり今風になっちまってます。
dさんへ
そうですそうです!昔は「妄想」し「熟成」させる時間がありました。
やっとこさ情報を入手するまでの「あこがれ」やら「勘ちがい」やらを含めた時間が、、、。正しいか間違いか、などという野暮な結論を度外視して言うと、あれこそが人として真にクリエイティヴな時間であった、と今にして思えるのですよ、おじさんは、、、(笑)。