私が個人的に好きな「アランブラ奏者」を挙げると、P.ロメロ、A.ラゴヤ、L.ブローウェル、
日本人では池田慎司、北口功、会所幹也(以上敬称略)。
もちろん私が知らないだけで、ステキな演奏をする方はこの世にたーくさんいらっしゃるはずで
あるが、、、。ちなみにみなさん御贔屓の”アランブリスト”は?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
え~、前回の続き。
*『②弦メロの時、左のあまった指で①弦をミュート』
これは多くのプロ奏者が実践していることであるが、要は保険である。
ひとつ上の弦を間違えてひっかけた時、”バシャ~ン”と響くかわりに”ボコッ”で済む、という
ただそれだけの話であるが、この保険をかけていることで、かけていない時よりも安心して
すこし大胆に指が振れる。その結果命中率も高くなる。
*『可能な限りローポジ運指にかえる』
ローポジすなわち”ロー・ポジション”のこと。
つまり出だしのメロディーから①弦開放弦を使うのだ。
「ええ~っ!?作曲者タレガの意図と違うじゃないか」などとキレイごとが言えるひとは、
まさかこの連載には目を通してはいまい(苦笑)。
それにタレガが作曲当初から出だしのメロディーを②弦でとっていたはずがなかろう!
楽譜に残されたタレガの運指は、普通にローポジで作曲された後、出版前の最終段階で付けられ
たものであることは明らかだ。はじめからこんな理不尽な左手運指を付けていたとすれば、
作曲者はよほどの変人だ(なにもそこまで、、、)。
アランブリストを目指す我々に必要なのは、まずこの曲を弾くに必要な最低限の技術的納得を
とりあえず手に入れる事。
タレガが作曲したのと同じ過程を辿りながら、最終的にタレガの希望する音色美学に行きつけば
よい。この場合運指が変わるのはほぼ A moll の部分だ。
*『 p が隣接する弦を弾くときはアポヤンドする』
まずそれが可能な箇所で全部実行してみて、あとはお好みでやりたいところだけやればいい。
p をいずれかの弦にのせた状態で a m i を弾くと、場所によっては非常に安定する。
P.ロメロがアランブラをレッスンしている動画がYou tube にあがっているが、彼もやはり
そのようにしていた。
(つづく)
アランブラ・メモ(その6)
| カテゴリー: |
|---|
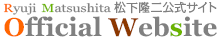

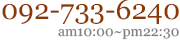
いつも拝読しております。
ローポジのお話、すごく、ありがとうございます!
中村さま
こちらこそコメントいただき有難うございます!
ブログで暴言的本音をまき散らしたり、YouTubeでハチャメチャな演奏動画を配信したり、右手指の爪を全部切ったりと、『ギター界の純粋主義者』を敵にまわし続けるような最近の私の活動にお付き合い頂き恐縮です。
でも「私が絶対的正義だ」などとはこれっぽちも思っていません。
むしろいろんな考えが存在していた方が健全なことかと、、、。
ただ、いつ後ろから刺されてもいいように遺書だけは書いておこうかな。
先生方の暴言的本音たいへん励みになります。これからも期待しております、刺されない程度に、、、♪
シリーズを拝読して、トレモロの技術的難しさもさりながら、先日目にした演奏で、左手の拡張も難儀そうで、課題を地道にクリアしないと、自分で弾いてみたい気持ちにならないという。
ローポジでよいって気が楽になります。
まずは、トレモロやってみる。カルカッシさんの七番しか浮かびませんでした。
Hongoさま
カルカッシの7番はですねえ、、、これまで割と普及してきたリョベート運指の楽譜『25のエチュード(全音楽譜出版社)』では冒頭部分がトレモロ運指(pami)になってますけんど、カルカッシ本人の意図に多分それは無かったはずなんです(本人的にはたぶんpimiもしくはpiai)。
同じ音の連続を”トレモロ”と呼ぶことは定義として間違ってはないし、そういう意味においてはあれも立派なトレモロではありますが、、、。
つまりアランブラのような『ギター独奏用トレモロ(32分音符表記)』と、あれ(16分音符表記)とは、本来技術的に明確に区別すべき事柄かな、、、というのが、私の見解です。
以上、訳がわからない話だった場合はごめんなさい(苦笑)。
トレモロとっかかりとして、まずは「フェステ・ラリアーネ」あたりはいかがでしょう?
なんと(衝撃)
涙目になっております。
(もう、トレモロの曲は聴くだけでいいのではないかと言う気分になっております)
いえいえ、だからラリアーネ祭など、、、。