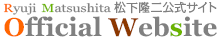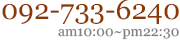「個人史には興味なくて・・・」という声が夢の中で聞こえ
はっとして目が覚めたのが二週間前のこと。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
二度目のペリー来航時、条約締結を祝う船上パーティーに招待された幕臣たちが、日本人として初めて目にした ”ギター” という楽器。それから時が流れ、1901年にマンドリンとギターをヨーロッパから持ち帰った比留間賢八が教室を開いたのが、日本ギター史の始まり。その門下には武井守成、齋藤秀雄のほか萩原朔太郎、藤田嗣治らも居た。
小原安正、阿部保夫各氏らの活動の時期からさらに時が流れ、日本人のギター・ソロ演奏の水準がヨーロッパでも認められたひとつの証が、渡辺範彦、山下和仁、福田進一各氏による《パリ国際ギターコンクール優勝》であったろう。一方で荘村清志、芳志戸幹夫各氏らの活動も、当時の日本ギター界に強い印象を残している。
ソロ演奏の水準を上げることに注力してきた日本人ギタリストの次なる課題は、アンサンブルであった。ギターによるアンサンブルのみならず、他楽器とのアンサンブル水準を上げるには、クラシック音楽に対し、さらに関心を広く持つことが必要になる。ソロの探求とは別に・・・。
まずは音楽の共通語でしゃべることを多くのギタリストが試みた。地方から都会に出てきた人間のように。だが ”ピアノのように” ギターを演奏しようとした結果、技術的にあっぷあっぷ状態になり、他楽器からは「これならギターよりピアノでやったほうが・・・」と思われるだけのものにしかならなかった。
つまり音数や技術で「ピアノに追いつこう」ではなく、ギターという楽器を生かすための《編曲技術》がカギになる、と徐々に気づいてくる。そしてそのヒントはすでにあったのである。ソル、ジュリアーニのなかに。タレガ、リョベート、プジョール、セゴヴィア、ブローウェルのなかに。
様々な楽器とのアンサンブルがうまく噛み合うようになると、次に進むのは他ジャンルの専門家との、敬意を伴う《越境演奏》。これは個人的見解だが、別に《なんでも器用にこなせるギタリスト》を目指す必要があるとは全然思わない。ただジャンルの違う相手がどういうスピリットに立脚して演奏の場に居るのかを、敬意をもって知ろうとするだけでよいのではなかろうか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そして十日後、北九州の地でコンサートが開催される。これは《クラシックギタリストの”いま” 》を体現するものであり、出演者10人だけによるものではない。過去の「日本人とギターとの関わりの蓄積」無くしては存在し得ない世界である。レオナルド、池田の音楽を主軸に、それをしっかりと受け止める気概を持った若者たちがそこにいる。そしてギターの歴史において最も重要なのは、愛好家の人達と専門家が手を取り合って共に進んできたその歩みに他ならない。専門家だけでワーワー盛り上がっても事態は何ひとつ動かない。
すべてそろっている。足りないものはなにもない。
2025.02.14.