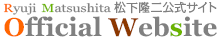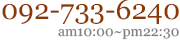先月東京で、とあるクラシックギター専門店を訪れた時の事。
そのお店は都内でも比較的落ち着いた雰囲気のところにあり、東京を徘徊するのにくたびれた
折、私が必ず羽休めに立ち寄るスポットのひとつである。
社長のSさんはお忙しいかたで、お店にいらっしゃらない事がほとんどであるが、この日は
幸運にもお会いする事が出来た。
わたしは最近の東京のクラシックギター事情が知りたくて、ある質問を投げかけてみた。
「最近東京で、いわゆる名器と呼ばれる楽器は動いて(取り引きされて)いますか?」
Sさんは答えた。
「、、、ほとんど動きませんね。」
ここで“名器”というものについて多少の解説が必要だろう。
十九世紀に活動したスペインのギター製作家アントニオ・デ・トーレス(Antonio de
Torres, 1817~1892)はそれまでの楽器制作の手法を大きく転換し、「音量の増大」と
「音色のクオリティ」を両立させる事に成功した。これはクラシックギターという楽器において
ほとんど奇跡的なことである。
トーレス以前のいわゆる「古典期」のクラシック音楽は“しゃべるように”演奏する音楽であり、
「多彩な音色」などというものは音楽そのものが求めていなかった時代である。つまり音色や
音の伸びよりも「アーティキュレイション(句読法)」のはっきり付けやすい楽器が必要と
されていた時代である。
ところがトーレスの生きている時代辺りから音楽界はメンデルスゾーン、ショパン、シューマン
らに代表される「ロマン派」の時代へと移り変わってゆき、それまでの「しゃべる(理解する)
音楽」から「描く(感じる)音楽」ヘと音楽そのものが変わってゆく。
楽器にもそれまでは重要視されなかった「音色の多彩さ」「音量の増大」といった要素が求め
られるようになる。以後楽器制作は大きな転換を強いられる事となったのだが、これは苦難の道
であった。ギターという楽器は、“音量を増大させる事”と「ハーモニーのバランス」や
「多彩な音色」を共存させる事が非常に難しい楽器なのである。
そして従来の手法を大きく変えることで、それらの事を高い次元で両立させる事に成功した
最初の製作家がトーレスなのである。
トーレスの製作したギターは一つの規範となり、「伝統的なスペイン・ギター」のルーツと
なった。たいへん乱暴な言い方をするなら、今現在のギター製作は「(トーレスを規範とした)
伝統的な手法で作る」か、「音量の増大を求めて、違う製法を確立する」か、もしくは
「それらの両立」が製作家によって模索されている状況といえる。
そしてトーレスの製作法をルーツにしながらも、製作家それぞれが独自のアイディアもしくは
美学を加え、世の演奏家の多く(特に巨匠ギタリスト)がすばらしさを認め愛用しているものを
ここでは“名器”と呼ぶことにしたい。
例を挙げるとスペインの製作家ならば、サントス、ラミレス一族の一部のもの、ロマニリョス、
フェルナンデス・イ・アグアド、アルカンヘルなど、、、
他にフランスのブーシェ、ドイツのハウザーⅠ世、Ⅱ世などである。
こっち方面(楽器について)のマニアックな話にはわたくし弱い為、ご興味ある方はご自分で
お調べいただければ幸いである。
要は今回それらの楽器の危機的状況についての話がしたい。
(つづく)
名器よ、どこへゆく、、、。(その1)
| カテゴリー: |
|---|