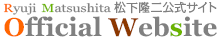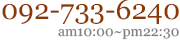私がパリにギター留学したのは94年、23才の時だった。
日本を代表するギタリスト福田進一さんのご紹介で、福田氏の師匠であるアルベルト・ポ
ンセ先生のもとで勉強させていただけることになった。
ただ事前の噂ではかなり厳しい先生だという事だったので、内心ビビッていた。
(実際は全然そんな事は無く、とてもあたたかい方だった。いや、ウソじゃないって、、、)
習い始めの頃はひたすら「如何にギターからやわらかい音色を引き出すか」に
エネルギーを費やした。その事に関してはおそらくクラスで一番手間取っていたと思う。
なぜならクラスの皆は柔らかい音の出しやすい“杉のギター”を使っていたが、私が日本
から持って行ったのは、日本国内でも「鉄下駄」の異名を取る松村雅亘氏製作の“松の
ギター”だったのだ。おかげで苦労した反面、いまではどんなギターからでも柔らかい
音色を引き出せる自信はあるが、、、。
ポンセ先生から受けた影響は決して小さくは無い。それについてはまた別の機会に
触れようと思うが、当時の私には巨匠のレッスンを消化できるだけの能力に欠けていた。
未熟だったというより、もっと未熟だったらおそらく幼児のように疑うことなく全身で
影響を浴びる事ができたのだろう。その頃の私は自分が弾こうとしているその曲の中で
“何が起こっているか”あるいは“作曲家が何を感じ、考えていたか”それを知る能力を
ひたすら欲していた(今現在もそうである)。
しかし“巨匠レッスン”に理由は無い。
ひたすらついて行くのみである。
ありていに言えば不満であった。
ある日いつものように楽譜を買いにパリ市内のギター専門店“ギタレリア”に足を踏み入
れた私は、店内でギターを試奏している中年のおじさんの演奏に釘付けになった。
貫禄と風格と気品を兼ね備えたおじさんのそばには御付きの生徒のような若者がいて、
「次はこれ弾いてくださいよ!」みたいなノリで売り場の楽譜を次々に持ってくる。
おじさんは「ははあ、、この曲か」と笑いながらモノともせず完璧に弾きこなしていく。
しばらく呆然と見ていた私は、まるで“水戸黄門”のワンシーンのように「あのー、あなた
様はどなた様で、、、」と聞くと、おじさんが一言「オレか?オレなんてどうでもいい。
彼はパブロ・マルケスだぞ」と向こうで楽譜を漁っている例の若者を指さした。
おじさんの一言は私を金縛りにするのに十分だった。彼がパブロ・マルケス??
彼が世界最高峰のパリ国際ギターコンクールを弱冠20歳で制覇したあのパブロ・マルケス??
世界にその名を轟かすアルゼンチンの俊英と目の前のお兄ちゃんがどうしても結びつかん。
そんな私を意にも介さず「じゃあ僕もこれ弾いてみよ~っと!」と初見演奏を始めた
パブロを見てさらに金縛りにあってしまった。(このひと全然ひけてへん、、、。)
帰りの地下鉄の中で私はひたすらつぶやいていた。
「“世界のパブロ”も俺と一緒で、初見は苦手なんだな、、、よかった、、、。」
(つづく)
唐人町ギター教室では、楽譜が読めない初心者の方からプロを目指している上級者まで、現役プロミュージシャンが丁寧に指導致します