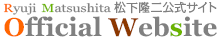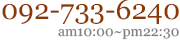今回話題にすることは、ギター教室の先生たちの多くが感じている、あるいは気付いていることだと思うが、公ではあまり言及されないことである。
個人的な話から始めたい。わたしはトレモロに対して長年、苦手意識を持っている。持っているからこそ「なんとかして上手にトレモロができるようになりたい」と、時にはうまい人の話を聞き、時には技術や意識を変化させながら長年に渡って挑んできた。
もちろんトレモロの曲を弾かなくとも、プロとしての演奏活動にそこまで支障があるわけでもない。だが実際の現実問題として『アランブラの思い出』を弾きたい生徒さんは数多く、レッスン機会も多いため、自分の中の問題点をせめて自分の中においては解決しておきたい、、、そう願ってきた。
だがズバリ、今回の話の核心を言う。プロでも愛好家でも、初心者でも30年選手でも、そんなこと関係なく、《得意なひと》と《苦手なひと》に分かれるのが ” トレモロ奏法 ” である。したがって教えるガワがレッスンにおいて大事なのは、まずその生徒さんがどちらか、を見抜くこと。そしてもし《得意なひと》だった場合は、極力余計なアドヴァイスをせず、ひたすら褒めながらあとは放置することである。<放っておくこと>と<仕事を放棄する>ことは似て全く非なるものであるから、別に自分を責める必要はない。
《苦手なひと》だった場合、、、そう、こちらの方が数としては多い。
ちなみに《苦手なひと》が《得意なひと》にコツを聴いても無駄である。なぜなら《得意なひと》は、身体の中に《苦手なひと》の神経回路を持ち合わせていないから、感覚的に「なぜ動かないかが分からない」ひと、なのである。
「ぼくもあれこれ苦労して習得したんだよ」と言われても、真に受けてはいけない。得意なひとと苦手なひとではスタート地点からして別の世界なのである。
では《苦手なひと》を生み出す要因はなんだろう。
一番は、自分の能力(反射神経)や意識(動体聴力)を超えた速度で弾こうとしていること。例えばペペ・ロメロやイエペス、ジョン・ウィリアムスの速度で弾くのが ” トレモロ ” だと思っていること。落ち着いて耳を傾ければ、速いひとを比べても、いろんな種類の速さがあり、ひとそれぞれでキャラが違うということに着目してほしい。
陸上の選手が、カール・ルイス(古いなあ)と同じタイムを出すために、毎朝、同じ時間に起き、彼と同じものを食べ、彼と同じ筋力トレーニングをしても無理なのと同じことである。なぜならカール・ルイスの身体の内部(つまり脳活動、神経系の回路と反射)を、その人は持っていないからである。
つまり、身体の反射速度などは、ひとによって様々。最も大事なのは「自分の身体と音楽が同期していること」であり、” ひとなみのトレモロ ” を弾こう、などと思わないこと。
そう、まず自分と同期させること。自分を超えたテンポ設定をしないこと。つまり自分のトレモロをやること。ひとのトレモロをやろうとしないこと。
以上がジストニア症状のリハビリのなかで気付かされた「トレモロが弾けない」要因である。
似ている。
2024.03.12.