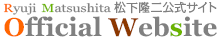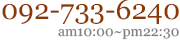自分のための思考訓練。
ジャンルの垣を越えるということはどういうことだろう?
もちろん「越える必要があるのか」ということも含めて検討が必要だろう。
「越えること=自由=いいこと」という安直な図式に疑問符を投げかけることは大切だと思うが、この場では一旦置いておきたい。
とりあえず考えられる道のひとつは、ポップス、クラシック、ジャズ、邦楽、民族音楽など、異なるジャンルのミュージシャンが集まった時、それぞれの専門的手法をミックスするサラダ的発想。
これはこれまで多くのミュージシャンがとってきたやり方だが、事前にある程度 構築されたものにせよ、即興にせよ、予想を超えた化学反応を起こすことは稀である。
これは本質的に “ミュージシャン同士の越境“ であり、音楽そのものが変質するわけではないから、、、ということもある。
ちなみに自分が体験したコンサートでは、過去に一度だけ予想を超えたことがあった。フォルクローレ音楽、ブラジル音楽のミュージシャン10人で共演のステージだったが、その時いい感触となった主な要因として考えられるのは、、、
*リーダーの采配のうまさ(方向はしっかりありつつも各メンバーに自由な余地を残していた)
*リハーサルを通じ、共演者同士たがいに尊敬し合う気持ちが芽生えていった
*メンバーひとりひとりの経験や実力が高かった(ひとりでもステージをつとめられる存在感を全員が放っていた)。
*演奏中フロントとバックスの役割の出入りに関して、全員が自主的に動いたが、例えばバックスにまわった時、単におとなしくするのではなく、音楽に火をくべ続けられることが強みだった。そしてフロントに出るときはバックに負けない存在感を各自が示した。
*レパートリーが“ラテン音楽”に限定されていたため、やりやすかった。(クラシックベースのミュージシャンは私だけであったので、ひとり右往左往していた、、、笑)
つまりこの時は、アレンジそのものの良さというよりは各自の自主性に支えられていた部分が大きく、Cメロ譜をもとに身の振り方を対処できるメンバーがそろっていたということだ。このとき私は自分のやることを、事前に音符化するか、コードで対応するか、のミックスだった。
クラシックミュージシャン以外は、音符で渡されると困るひとが多い。そのため越境演奏の時は、クラシックミュージシャン側がコード・アプローチに対し、自主的に対応するほうが話が円滑に進む。つまりこれまで何度も言及してきたように、音楽界全体においては、われわれクラシックミュージシャンの方がマイノリティである、という自覚が必要なのだ。
ここまでは越境演奏についての話だが、ここからは音楽そのものの越境、つまり“越境音楽“について
音楽面に関しては、1900年以後ヨーロッパ中心主義の時代が終わり、ドビュッシー、ストラビンスキー、バルトークなどに代表される “他の文化圏から刺激を受けた創作” が始まる。これはヨーロッパがそれまでのように独自で創造してゆくエネルギーを失ってしまったことに起因するが、民族音楽、ジャズ等の大衆音楽から手法だけを抽出し、クラシック音楽に還元、反映させるというのは、結果として「第三世界からヨーロッパが搾取する」という植民的関係のあらわれに過ぎない、と言うひともいる。しかし一方で、ピアソラやマイルスがクラシックから影響を受け、自身の世界を拡げたことについては、逆の立場だから非難されない。
これらすべて含め、私は越境音楽のうまくいった例だとみている。つまり個人がオリジナルとなってゆく手法だ。
21世紀の現在、ひとりのミュージシャンでありながら複数のジャンルに精通しているような若手がすでにたくさん出てきている。音大でクラシックの作曲法を学び、同時にジャズの即興も出来、民族楽器を手にするかたわらで、ゲームのための音楽を製作したり、、、という “自分の内部で越境している” ミュージシャンが、世界のあちこちで活躍を始めている時代である。
そういったなかで「職業的作曲家が、音楽を創作する」という構図が、この先も必要とされるかどうかはわからない(音楽産業界には必要かもしれないが、音楽を愛好するひとびとにとって必要か、ということ)。
わからないが、自分たちの生活があたかも世間から保護されているかのように錯覚しやすいクラシックミュージシャン種族は、これまでのように世の流れとは違う時間を過ごすだけでは、気づいた時には価値を失い、居場所がなくなっている可能性が充分にある。
2022.10.24.