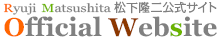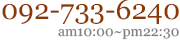”過去”と”歴史”が違うものだとした場合 歴史はいつから歴史になるのだろう
リアルタイムを知っているひとが死に絶えたときか?
私にとって《学習》とは 過去の事例にさかのぼり 現在の自分と結びつけること
ジャズメンは例えば バード モンク マイルス コルトレーンのアプローチの仕方を学び 自分と結びつける
クラシックミュージシャンは 作品の中でなにが起こっているかを知ろうと努め 自分と結びつける
パリ・コミューンの中で生まれ 労働者をつなぐ歌として 世界の社会主義運動に広がった ”インターナショナル”
旧ソ連では 1918~1944年まで この曲が国歌だった
治安維持法下の日本では 歌うことを徐々に禁じられてゆき
歌詞をラララにかえて「ラララ行進曲」として歌われたが それもやがて禁止
言葉を封じられても歌うことをやめない「ラララ~」の方が「インターナショナル」より個人的には凄みを感じる
私にとっては アレア トスカニーニ 武満・・・
少年時代のプーチンが憧れたソ連の諜報員ゾルゲは 絞首刑になる際 日本語でこう言った
「これは私の最後の言葉です。ソビエト赤軍、国際共産主義万歳」
篠田正浩監督の映画『スパイ・ゾルゲ』の中では このゾルゲ処刑の場面で 鈴木大介氏のギター演奏によるインターナショナルが静かに流れる
ちなみにこのギター版は 武満編でなく池辺編である
中学生の頃 父の書庫の中から なぜか大逆事件および幸徳秋水関連の書籍を抜き取り 読み漁っていたそんな時期があった
中江兆民、田中正造、堺枯川、片山潜、大杉栄、、、
彼らの手足を封じ じわじわと追い詰める国家権力の不気味さだけが 当時妙に印象に残った
父とは生前ろくに話をした覚えがない
私が反抗的だったわけでもなく もともと寡黙な父であり 仕事部屋にたえず籠っていたが 直接交わす言葉以上に その背中だけで どうも男親というものは影響を与えてしまうものらしい
1958~1960年 サークル村で詩を書き続けた父のなかで ”谷川雁の存在” は 生涯にわたり神聖さを保っていた
炭鉱での文学活動から離脱し 学生運動に身を投じるには早すぎた父にとって 安保闘争のはざまで流れるインターナショナルのメロディーは 『11月のある日』の主人公でありキューバ革命のかつての闘士エステバンが 革命後の若者風俗に感じたのと同質のよそよそしさだったにちがいない
オリンピックが代理戦争のように<国家別に>おこなわれるいわれは 本来ない
ナショナリズムという言葉は(アナキズム同様)誤解されていることが多いが 互いの国民性の違いを認め 自国の文化を大切にすると同時に 他国の文化に最大限の敬意を払うことが ”ナショナリズム”の真の定義である
レノン氏は ああ言うが
国境は文化を形成している言語圏に沿って 存在したほうが良いと思う
大切なのは国境がないことではなく 他者に敬意をもちながら 自由に越えられる環境ではなかろうか
つまりナショナルあってこそのインターナショナルという 当たり前の帰結
仮にすべての人類に 世界どこの国で暮らしてもいいという権利が 無条件で認められたら どうなるだろう
生活がより快適な国へとそれぞれが移動し始め 国を運営するのに適正な人口を確保するために国家は躍起となって引きとめ(あるいは追い出し)にかかるだろう
国民を支える国家は支えたいが
国民を踏みにじる国家は 国民によって支えられる価値もない
国家や法(警察)が 実質上存在もしくは機能していない地域での人々の生活は 果たしてどうなるのか
実は全くなんの支障もないという事例が 世界のあちこちに存在している
================================
起て飢えたる者よ 今ぞ日は近し
醒めよ我が同胞(はらから) 暁(あかつき)は来ぬ
暴虐の鎖 断つ日 旗は血に燃えて
海を隔てつ我等 腕(かいな)結びゆく
いざ闘わん いざ 奮い立て いざ
あぁ インターナショナル 我等がもの
いざ闘わん いざ 奮い立て いざ
あぁ インターナショナル 我等がもの
(佐々木孝丸 / 佐野碩 訳詞)
2021.08.09.