音楽の本質は”和を以て貴しとなす”
マイルス・デイヴィスは自叙伝でこう言い残した
「音楽は絶対に競争じゃない。協調だ。」
自分と楽曲の協調、自分と楽器の協調、演奏する人と聴く人との協調、、、
過去の自分とも競争はしない
自分の過去と協調しながらやっていく
コンクールも決して他者との競争ではない
世にあまたある楽器のなかで
独奏コンクールが存在する楽器のほうが少ないという事実に目を向けてみればわかる
”コンクールの結果”というものは、音楽の本質から遠いところにあるのだ
特に音楽を仕事にしているひとは
協調の精神ひいては平和について世の中に投げかけるのが仕事だ
本人が自覚していようがしていまいがそれが役割だ
(必ずしも具体的なメッセージというわけではなく、もちろん音を通じてだが)
自分の根っこをそこに持ってないと
音楽を生業にしている意味が無いのではないか
国家権力どうしの争い、大中小企業どうしの競争、専門家や研究者間での競争、、、
そういったものにからめとられぬよう一定の距離を置きながら
今年も音楽を通じて自分の技術や感覚、感性、、、
そしてヒューマニティーを育ててゆきたい
音楽は自分と異なる価値観を受け入れるためのエチュードと成りうるのだ
2020.1.7.
いちミュージシャンの年始御挨拶
| カテゴリー: |
|---|
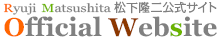

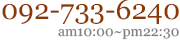
ブログの内容から脱線事故をおこしそうですが、すみません、コンクール、というものはなにゆえの存在でしょうか?
世界的コンクールの審査員の方(ピアノ)が、ソリストで今後やっていける証明書です、と仰せでした。でも、消えていく方もいますよね。
ここ最近、「ミュージシャン」が、体制による、もしくはよらされることが多いような気がします。大衆に近い「芸能人」は、プロパガンダを担うしかないのでしょうか。
何かを観るとき、聞くとき、俯瞰でいたい。
寄り添うときは、ただ黙って疲れた方のそばにいたい。
そんなふうに音楽を、大事な方と自分のために、何を気にせずことなく立っていたい。
阿る必要のない時代でいてほしい、そう願っています。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
(BGMは、なぜかのニック・ドレイク、ピンクムーン)
S.Hongouさま
コンクールの存在意義ですか?なんでしょうね、、、
「自分がやっていることの価値を判断できないひとが、その業界の権威に判断してもらうことで承認欲求をみたすため存在する」
「なお有名コンクールで得た賞歴は、メジャーレーベルや音楽事務所との契約時に多少は効力を発揮する」
思いつくことを本音で書いたのですが、これって酷い言いざまですか?
現在の僕には縁のない世界ですので、見る人が見れば《負け犬の遠吠え》ってとこでしょう。それも否定はしません。
ただ”メジャーとマイナー”とか”表舞台と裏街道”、”第一線”から”消えてゆく”などという世間でよくある言い回しは、僕からすれば幻想に過ぎません。
「やりたい音楽が目の前にあって、聞くひとが目の前にいる」
音楽活動ってそれで充分ですから。
〉やりたい音楽が目の前にあって、聞くひとが目の前にいる」
音楽活動ってそれで充分ですから
本日(もう昨日ですね)の、ミュージックフェスティバルを、演奏者も聞いている人も、いる人にしかわからない熱情を堪能しました。これが聞きたかった、感じたかった。あらためて実感しました。
大ベテランのみなさまが、若手ミュージシャンをもりたて、異業種ミュージシャンにも敬意があり、得がたい体験でした。
ありがとうございました。
S.Hongouさま
あっ、そういわれてみると今回のはおっしゃるように様々な要素がうまく満たされていましたね。
でも当人たちには分からないもんなんです。演奏した人間は演奏後、自分が間違えた1小節のことしか頭にないのです。
でも帰りにみたお客様のお顔の印象は「たぶんそんなには悪くはなかったんだな」という感じでした。
ミュージシャンは毎回それに救われるのです。