日本を代表するラテン・パーカッション奏者、渡辺亮さんと共演させて頂いたのは
2011年5月栃木県佐野市で行なわれた木下尊惇ユニットによる「しあわせの架け橋」公演
での事だった。
亮さんは二日間(全三公演)にわたる演奏でそのアーティスティックなパーカッションセンスを
披露し、客席はもちろん我々共演者をも魅了したが、実は亮さんには仲間内でも知られている
もうひとつの側面がある。
なんと“妖怪博士”なのである。
それは単に詳しいなどというレヴェルではない。美大出身であるご自身の手による様々な
妖怪たちのイラストワークは、もはや知識や趣味の領域を通り越して“愛”を感じる。
(ご興味ある方はぜひこちら)
その亮さんが公演終了後、ホール駐車場での雑談のなかでこうおっしゃっていた。
「妖怪の存在って世の中にとって何の役にも立たないんですよねー。」
なぜ私がその一言を覚えているかというと、“役に立たない”とおっしゃった時の亮さんの声の
響きが、私の耳には“誇らしげなもの”に聞こえたからである。
“役に立つ”“便利”といった言葉をプラスなものとしてしか捉えない人が多い。
私はこの二つの言葉を聞くといつも反射的に警戒してしまう。(それもどうかと思うが、、、)
「必要じゃなければやってはいけないという思想があるんですよ。それが資本主義。逆に、
必要だからやらなければいけないということになるでしょ。それは社会のためになるからやらな
ければいけないと。その社会っていうのが何かというと資本主義社会なんです。だから、資本に
奉仕しろという意味です。だから、それならばなんにも役に立たないことをやるべきだと。
お金は浪費するべきだし、働くということがいかによくないかということを、遊びでもって
みせるべきだということ。(中略)なにが役に立つんだろうと言ったときに、もう社会に奉仕
するというところに組みこまれていく。「役に立つ/役に立たない」、この二項対立そのものが
啓蒙主義なんです。」(高橋悠治~アルテスvol.1インタビューより)
「ぼくは音楽による政治参加は不可能だと思うのです。音楽が政治的な効用を果たすとすれば、
それはもう音楽ではなくて政治です。ぼくはさっきも言ったように、音楽をやりたいので、
政治をやりたいのではない。音楽をやるということに人間としての充全の意味を感じている。」
(武満徹~創造の周辺/芸術現代社より)
わたしは“音楽”というものは音楽のためだけに存在して欲しい、と思っている一人である。
音楽を“何か”の役に立てようとするのは、好きでない。
「妖怪」と同じで「音楽」は、何の役にも立たないものであってほしい。
そうであるからこそ音楽の中に全身全霊で飛び込んで人は遊べるのではないか、、、。
2013.10.24.
役に立つ?
| カテゴリー: |
|---|
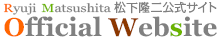

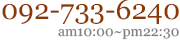
妖怪、というお話には食いついてしまう人です。
妖怪は、やくにたたないものではないのですよねー、その背後にはいろんなものが潜んでるんです。
ただ、それをこうるさく難しくいっていては、誰も聞いてくれねぇ。
たとえば、風呂場に出てくる「あかなめ」なんて、掃除はちゃんとしろよ、という昔の人からのメッセージだし。
この世界、妖怪や物の怪が安心して暮らせる、薄暗い場所が消えてしまって久しいですが、自然の中に畏敬がいまだに我々の心にあるかぎり、「妖怪」はきっと、形を変えて滅びていくことはないと思います。
そうですね。背後にはいろんなものが潜んでいるでしょう。ただ「大切なもの・かけがえのないもの」=「役に立つもの」という言い回しで言い表したくはないし、「役に立たないもの」が即ち「大切でないもの」とも言えない。「役に立つ/役に立たない」という言葉に対する一面的な寄りかかり方に対して私はいささか懐疑的です、という今回の話でした。