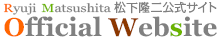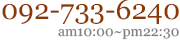とは言ったものの 私が過去に好きだった他者の演奏を思い起こすと そのことはあまり重要ではないのかもしれない
曲の構成を感じさせる演奏
ギターという楽器の音の美しさを感じさせる演奏
それまで気づかなかった”ある声部の動き”に目を向けさせてくれる演奏
バルカローレの世界を感じさせる演奏
ロマン派の世界を感じさせる演奏
バリオスの世界を感じさせる演奏
など それぞれに価値があり 正解などないのだから
ただ自分が目指すものに対して 可能な限り”妥協点が高い”ことが 私にとって大切で この記事を読んでくださった方が 「いや、自分はそうは思わない」とか 「私は他の〇〇のことを大切にしながら弾いている」というふうに ご自身のとらえ方を整理するのに活用してくだされば本望である
私なりの旋律アナリーゼを右に示す 松下流 Julia Florida 旋律大雑把把握
この曲に使われている要素でおもしろいなと個人的に感じるのは
*五度音ラを軸にした場面A
*各場面で印象的に使われる二度音程の揺れ
*Dメジャー、Dマイナー各コードの中で ときおり印象的にあらわれる六度音シ
*場面Cにおける調性の動き
といったところ
6 / 8 のなかで舟歌として揺れ続けることになるが 4拍目のほうが1拍目より浮いた感じが出ることが大切だと感じている その際2・3・4と浮いてゆき 5・6・1と落ち着いてゆく
場面Bの5小節目であるが ここからの4小節を弾くときに三拍子のノリで弾いたほうが 私の場合時間を持て余さずに済んでいる あくまで個人的趣味の域であるが そうしたほうが「シのオクターブ跳躍を六拍子のなかで情感豊かに表現する」といった束縛から解放されるのだ

場面Cに入るひとつ前の小節 「1拍目のバス Fis は絶対におかしい」と主張する友人がいる 多くのギタリストは既に耳が慣れすぎてしまっているが 彼の言うことはスジは通っている すなわちA7のコードトーンがくるほうが作曲としては自然であり そうするとこの場合ラである可能性が最も高い あくまで可能性の話である
あと楽譜上は割愛したが コーダのライトハンド・ハーモニクスのラスト ベニーテスでもレの版とシの版があるのはご存じの通り レは言わずもがな曲の《主音》であり シはこの曲中 印象的に使われ続けた《六度音》 私は好みで六度音をとるかな どうせ最後はナチュラル・ハーモニクスの主音でしめるのだから
(おわり)