 先日キース・ジャレット・トリオのコンサートを聴きに行った東京で、かれこれ二十年来の友人であるギタリスト、鈴木大介くんと久しぶりにゆっくり話が出来た。
先日キース・ジャレット・トリオのコンサートを聴きに行った東京で、かれこれ二十年来の友人であるギタリスト、鈴木大介くんと久しぶりにゆっくり話が出来た。
ここ数年彼は大変忙しい身なので、このような機会は私にとってありがたい時間である。
彼の話はいつも私の脳を活性化させてくれる。
今回の会話の中でとくに印象的だったテーマのひとつは、
“東京のミュージシャンと地方のミュージシャンのスタンスの違い”
についてだった。
鈴木くんは
「音楽をピュアに突き詰めるには、地方にいるミュージシャンの方が有利だ」
と言うのである。
前々回のわたしのブログ(外国人として)の内容にもつながる話であるが、
東京はあらゆる分野の最高峰の人達が来日して、毎日のようにコンサートを行なっている
世界でも特殊な街といえる(このあいだやってたフラメンコのカニサレスもそうだし、
もちろん今回のキースも、、、)。
つまり“本家家元”がぞくぞくとやってくる「東京」という街で、本家をリスペクトする
ことはあっても、そのコピーなどやっていて太刀打ち出来るわけがない。
ではどうすれば太刀打ちできるか、、、。
日本人として、あるいはひとりの一個人として、伝統とは別の価値を確立する。
もしくは“本家が(本家であるがゆえに)出来ないアプローチ”を描き出すしかない。
だから東京ほど本家が頻繁に訪れない「地方」のほうが、むしろ本家を最大限リスペクト
しつつ、洗練された世界を追い求め易いのかもしれない。
“日本人としてのアイデンティティー”や“個人的なキャラクター”を打ち出さざるを得ない
東京のミュージシャンのほうが、結果地方よりも「泥臭い演奏」になるというのはなんと
皮肉な、、、。
もっとも以上のことを踏まえて演奏活動している“東京クラシックギタリスト”が果たして
どのくらいいるのだろうか?(“地方クラシックギタリスト”もしかり、、、)
しかし“東京ギタリスト”と“地方ギタリスト”のスタンスの違いがあるとはいえ、
お互いが「関係ないね」とそっぽを向くのではなく、リスペクトし合いながら
どのように手を取り合ってやっていけるか、を考えてゆきたいね、、、
と、まあ以上のような結論になった。
もちろん他にもいろんなテーマ(来たるべき次世代のクラシックギター界について、とか)
を出してもらったが、それはまた追々、、、。
2013.5.13.
東京ギターと地方ギター
| カテゴリー: |
|---|
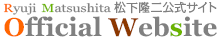

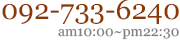
こんばんは。
お江戸の有名ギタリストの演奏を聞く機会はほとんどないのですが、私はこの地で、先生型の演奏を聞けて、本当に聞く姿勢と弾く姿勢をおしえていただいているような気がします。型にはまらない自由さ、独創性。この地方(国)ならではではないでしょうか。
ところで、先生の熱狂的信者によりますと、先生の文章には、なんともコメントがしにくいそうです。それは先生が、すべてのことに自ら答えを導きだし、それがまっとうで、なんともうなずいてしまて、もう書き込むことがないとか。
そんな信者の方から貢物をお預かりしております。
お楽しみにしておいてくださいませ。
そうですか、いや、そうですよね。
僕がその時々で出した答えなんか偏見に満ちていて
とても「まっとう」とは、、、。
しかしあんな拙い身勝手な文章でも読んでくださる方がいらっしゃるのですね(感激!)
くれぐれもよろしくお伝えくださいませ。