第二イントロの後、こんなかんじですが、、、


場面Aのメロディー二拍目のラの上のアクセントは、「ここから唄いはじめて、次の小節一拍目
ラまでが”ひと区切り”」という意味合いにとることが出来る。つまりただ強く弾くだけでなく、
三拍目表をこえて裏の”ソ”につながってゆく持続感がポイントである。
なお合奏版において、ここの 2nd. 3rd. 4th. パートは、管弦楽風(あるいはチャピ風)になる
よう、スタッカートによるアーティキュレーションを推奨している。
そして基本インテンポであっても、セレナータ特有の「前に進む感じ」は失いたくない。
オリジナルであるギターソロ版は、場面Aの7小節目後半からアッチェレランドがかかり、
カデンツァじみた雰囲気を醸し出しているが、合奏においては(チャピのように)テンポのまま
いく為、タレガの指示している4拍目アタマ”レ”のテヌート(ten.)は実現しない。
だがここは前回お話した、”イントロ予告”とのちがいを比較するためのニュアンスとして、
ソロ版ではぜひこだわりたいところ。「イントロで出てきたミじゃなくて、このレが本命だよ」
というのを(強さではなく)長さで示してほしい。

あと「そんなのあたりまえじゃねーか」と言われるかもしれないが、以下のアルペジオの
相似点と相違点を比較して、マイナー感とメジャー感をそれぞれ描き分けよう。


こういったことは一旦練習に取り掛かりはじめると、どんどん考えなく、あるいは感じなく
なってしまうものだ。なぜなら弾いてる最中は「間違えず弾けるか」が最重要事項になり
最大関心事になってしまいやすいからだ。
ギターをちょっと脇に置いて、珈琲片手に《楽譜を眺める時間》がいかに大事なことか
(珈琲じゃなくてもいいですよ)。
”どう弾くかのプランニング”、、、それが定まらないままギターを手にし、やみくもにギターを
鳴らしていると、自分の関心が「間違えたか」「間違えなかったか」ばかりにいくのは、
まあ当然と言えば当然である。
オリジナル版ではラストの小節に入る直前、フェルマータがかかる。
突如引き延ばされるドミナント和音、、、、、
聴いている人達の大半は、次に”ごく普通のDマイナーコード”を想定するに違いない。
だがそこで響くのはトニックのハーモニクス。
つまりこの曲の冒頭でひびかせたドミナント・ハーモニクスの返事をここですることによって
曲のアタマとおわりを一挙に繋げたのである。
その後しずかに響く、想定よりも一オクターブ高い、最後のDマイナーコード、、、。
今風に言うと、こういった”ネタの回収作業”ができるということが、重要な作曲技術のひとつ
とも言えるのである。しかし、ただなにげなく弾いていると、自分にとってそれが当たり前の
ことになってきてしまう。そうしてリアリティが消え、演奏は死んでゆく、、、。
私が演奏に際し常に心掛けているのは、曲の中で起こっている(一見当たり前にも思える)
そういった出来事にさしかかる度、「びっくりする」「関心を持つ」「強く感じる」こと。
映画や小説で、仮に先の筋がわかっていたとしても、その瞬間が来るたびに人間は幾度でも感動
することができる。それは神が人間に与えた恩寵のひとつ、、、、ナディア・ブーランジェが
そんなことを言っていた気がする。
(おわり)
2020.8.29.
『Capricho Arabe』の周りで(その4)
| カテゴリー: |
|---|
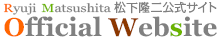

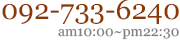
今回のシリーズ、アンサンブル科のレッスンで聞き逃していたり、忘れていたりを復習、再発見できました。ありがとうございます。
ギターを手にし、パート譜だけだと、間違って弾かない、でがつがつしてしまいます、はい。
スコアを見ながら読ませていただきました。譜面を眺める、読んでいく、がもっと楽しめるようになりたいです。
S.Hongouさま
いつもありがとうございます。
重奏にしろ合奏にしろ、アンサンブルのポイントは如何に”自分以外の音を感じながら弾くか”というところですが、そのためには自分のパートに対するある程度の心の余裕、そして前面に出るにしろ、裏方に徹するにしろ”自分の役割をわくわくしながら弾けるか”が大切だと思います。