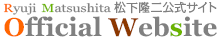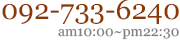《2021/4/22》
ここ数日停滞気味だったリハビリだが 今日またひとつの別なやり方に気が付いた
同じ動作反復がタブーな中 計画的なリハビリは持続するのが困難だと ここ数か月身に染みているのだが 突破口となりうるものはやはり “動かし方の種類”すなわち 運動のヴァリエーションを増やすための試行錯誤をつづけることではないか?
左ももにギター底部の側面板をのせ ネックを左肩に背負う感じ(実際は背負わない)
結果 弦の高低は逆に位置することになる
これでa,m,i,のタッチの方向はダウンになる(pが逆にアップになる)
右腕と楽器は接触がなくフリーな状態
D.レイズナー氏の言っていた「腕を使って水滴のようにフォーリンアップ」が《フォーリンダウン》で体験できる
次に左ももにギター底部の側面板をのせ ネックは地面と垂直に立て 表面板は右斜め前方にやや傾ける
右腕と楽器は同じ角度で平行に並ぶため 接点特有のプレッシャーはない状態
a,m,i,も pも 横方向に動くため ダウンもアップもない状態
次に右ももに・・・
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
《2021/4/23》
今朝、YouTube側がチョイスしてきた以下の動画を見た
2002.7.22. から 2004.3.13.までの期間 ジストニアが徐々に改善してゆく状況を記録した映像だ
スタート時点の症状がわたしと酷似している
( i 指の巻き込みによる空振り症状)が 約1年半の期間で見事に克服している
テンポ設定は私から見ると、常に速目でやや危険に見える(題材に使っている曲の難易度が高すぎるように思える)が
やはり i 指を意識的に前方に伸ばし巻き込みを回避することからリハビリを始めている(p,m,aをひくときにもそのことを意識)
私の見たところ2003.5.16.の時点ですでに完治と言っていい(つまり約10か月で)
一見したところ D.レイズナー氏の言うような、「うでの大きな力を意識」しているようには見られない
前腕から先の動きだけでリハビリに成功しているひとつの例だ
正直驚いている・・・
もちろん慎重にリハビリを続けるつもりだが これはひとつの希望にみえる
~~~~~~~~~~~~~~~
《2021/4/24》
昨日の動画を詳細に見始めた
二日目(7.23.)の練習は興味深い
あらゆる右手パターンをかなり速いスピードで ストップウォッチできっちり10秒計ってやらせている
i,m m,a i,a p,i p,m p,a アルペジオ・パターン トレモロ など、、、
この日の後半は器具を装着した練習が記録されている
次は器具をはずし、i を大きく前に伸ばすことを意識したパターン練習
ジュリアーニの『Allegro』
p,m のフィゲタで i を伸ばし切って練習
p,i,m のアルペジオで i を伸ばした練習
7.26.も同じ練習 症状はまだある状態
7.29. 器具をつけた練習はおおぶりで外しているが 器具を外した状態では明らかに改善がみられる
まだ i を意図的に前に出している感じはある
8.2. タイムを計って以前のような練習 現在の私と同じくらいの状況
~~~~~~~~~~~~~~~
《2021.4.29.》
福岡のコロナ感染者数が急速に増えている
二日ほど前からマラッツを練習し始めた リハビリとは関係なく完全に趣味
p,i,m三連辛し
*今日思いついたリハビリ練習
i 指を2弦にのせて a,m を使って①②①②~
( i 指を前方にキープする練習)
2弦上の i が力が抜けているのを毎回確認する
これはたぶんいいリハビリ a にpの動きを足してもよい
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
《2021.5.1.》
《毎月あたまに記録動画を撮ること》を本日からスタートすることにする
もっと早くからやっておくべきだったが この気持ちになるまでには時間を必要とした
大切なのは素材の設定 症状があらわれるもののほうがよい
「pim」「mip」「pami」「pima」(以上、単発と連続と)
「pimami」「pimiaimi」(以上、カルリのコード進行で)
「禁じられた遊び《前半部」」「カルナバリート」(以上、ゆっくりと快速と)
こんなところだろうか
~撮影終了~
見返してみておどろいた
自分では多少良くなっているつもりだったが 実際ほとんど改善されていない
撮影時の緊張を差し引いても 弾いている本人のイメージと実際が ここまでかけ離れていたことに驚き
i は思った以上に巻き込み p はリラックスできていない
観察して慎重にやることだ 一か月後がたのしみ
「pimami」のとき
i を振ってすぐに脱力し、元の位置に戻すこと(福田タッチ)が大切だと思う
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
《2021.5.2.》
やはり昨日から心がけている<福田タッチ>はリハビリに重要だ
<指を振りぬいたまま>のスタイルはジストニア症状にとってはよくない
どの指も基本「振ったらすぐ元の位置に戻す」
今日気が付いたのは m を弦に載せたときはよくても
m を振ろうとした瞬間に起こる i の巻き込みだ
これが起こらないよう意識してゆっくりと練習している
~~~~~~~~~~~~~~~
《2021.5.3.》
今朝、池田氏からの電話で興味深い話を聞いた
スペイン・フェスタの打ち上げで「プジョール教本」の見直しをテーマに語ったそうだが その中に「当時“アポヤンド“”アルアイレ“の概念はなく、アポヤンドを基礎的動きとして捉えていたふしがある」「単に響きを混ぜたくない時に弦に触らないのがアルアイレ」「奏法として区別する意識が強いのは日本独特の現象かもしれない」というものがあったそうだ
現にジストニア症状の場合、アポヤンド奏法には何の影響もなく 楽な奏法なのである
これは今後、話を膨らませていきたい話題の一つである
~~~~~~~~~~~~~~
それとは関係なく今朝、意識にのぼってきたことのひとつ
右手タッチには“単独動作“とはべつに
複数の動きを一息で連続しておこなう“連動動作“がある
リハビリはそれぞれ分けて取り組んだほうがよさそうな気がしている
単独動作に習熟することは 間接的には連動動作のリハビリにつながっているかもしれないが
技術として別な可能性もあるからである
他の指が影響を受けることなく ある指を動かせることが
連動動作のときほど条件として大きい
~~~~~~~~~~~~~~~
《2021.5.4.》
回復には段階があると思うが 現在までの自分の場合の回復の段階を記録しておきたい
*リハビリはじめ(3月ごろ)は、とにかく肩、背中から腕を動かして 単独で指一本一本を動かすことに意識を集中 前腕だけを使ったタッチは封印していた
*4月に入り i 指先の引っ掛かり感や突発的反射運動はほとんどなくなりつつある この頃から素早い連動、前腕のみによるタッチも試している
いまだ速いテンポでの曲演奏は無理があるが、感触としては良好
カルリの『エゼルチシオ』は様々なアルペジオ・パターンが入れ替わり出てくるので リハビリには向いており ゆったり目のテンポ設定で毎日演奏している
*5月に入り、弾弦後に指をフォロースルーしない福田タッチを導入 速い音群での i 指の空振りは時々ある
マラッツなど練習を始める 三連アルペジオに違和感が完全になくなれば完治と判断できそう
m を動かすときの i 指の巻き込み状態が無意識時でも改善されれば これも完治の判断基準の一つとなる
フィゲタ回復もひとつのカギである
P の意識をしっかりと持ち、i はそれに付随する感覚
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
《2021.5.5.》
<単なる言葉遊びのようなもの>
単独動作するときの一つ一つの脱力状態(福田タッチの状態など)を“初期化”とよんでみる
ひとつの動作(発音)のあとには必ず初期化する
初期化が済んでいない状態で次の動作の準備に入らないこと
連動の場合は ある動きから次の動きへと数珠つなぎ的にリアクトしてゆくものなのか
じつはその音群を弾く前に 右手が“すべてを弾くための態勢”にすでに入って準備されているものなのか
どちらだろう
どちらも かもしれないが
先月半ばあたりからは とくに後者を意識している
以前は弾弦動作を終えると 次の右指をすぐに弦上にセットしていたが
弦に触れない宙ぶらりん状態の時間をたっぷりめにとるのが 初期化には効果的
~~~~~~~~~~~~~~~~
《2021.5.6.》
昨夜 R.ヴィアゾフスキーの動画を初めて見た
ジストニアによって彼自身に起こった体や意識の変化について
30分程度の時間 淡々と語ってゆくものだった
彼の場合は 3 の指の巻き込みらしい
巻き込みを制御する独自の意識的解決法 身体的解決法を作り出したそうだ
美しく語りすぎているきらいはあったが きっとロマンチストなのだろう(笑)
共感できる言葉は多かった
他者の影響を受けるというのは 良い意味でも悪い意味でもマイペースを崩されることだ
今朝のリハビリには影響された他者の意識が入ってきているためか いつもどおりにはいかない感じがする
きっとこういう感覚も必要なのだろう
毎日いろいろ刺激受けたり 思いついたり どれが重要なのかわからなくて大変だ
どれかのやり方に特化して焦点を当て過ぎないために 適度に散らしておいたほうが良いのだろう
しかし昨日の“初期化”は比較的 重要な部類に入ると思う