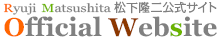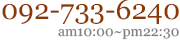「質問とは可能だろうか?」
いきなりなにを言い出すんだ、、、と思われるかもしれない。
だがいまだかつてこの問いを自分に投げかけたことのないひとは、一度でいいからこのことを
真剣に考えて欲しい。
近年はどうか分からないが、従来、邦楽の世界においては弟子が師匠に質問をするというのは
許されなかった。このことを聞いた人の多くが「なんて厳しい権威主義のタテ社会だろう」
と、ひとまずは感じるかもしれない。確かにそうかもしれないが、私には《質問してはいけない
理由》は別にある気がする。
”通し練習”を師匠と共になぞるだけで、その日のおけいこは終わり。師匠からのコメントも
なければ、アドヴァイスもない。
”理解”経由で《実演にむかうことの困難さ》にぶつかるよりは、師匠の演奏中の佇まいから
発せられる感触を入口とし、結果”理解”に向かうというコースの方が、仕上がりが確実で
はやい、、、
という事を”楽譜を介さずに演奏する世界”の方が、あたかも知っているかのようである。
そのことに加えて《質問》とは、ある景色が”見えないひと”から”見えるひと”に向かって
発せられるものなだけに、「そこはこんな景色ですよ」といくら言葉で伝えられたところで、
自力で辿り着いて眺めてみることに比べれば所詮ヴァーチャルにすぎない。
そこで最初の問いをいまいちど考えてみて欲しい。
「質問とは可能だろうか?」
だからといって”質問”という行為自体が無意味かというと私にはそうとも思えない。
レッスン時、講師にとって重要なことは、「その生徒さんがより前進するために何を伝えれば
よいか?」を探ることであるが、ただそれを伝えるだけでは単に「結論を受け入れろ」という
話で終わってしまう。その”一方通行な時間”にコミュニケーションはもはや成立していない。
生徒が聞きたいことを引き出し、講師が伝えたいこととすり合わせること。
聞きたいことと、専門家が伝えたいことのミスマッチを可能な限り減らす時間をつくること。
これら(いわばコミュニケーション)が現代の音楽レッスンには求められており、”質問”は
生徒から講師に向かって開かれた窓の役割をしている。
それを認めない邦楽の世界は、いわば師匠が弟子を最短でうまくすることを目指した(考え様に
よっては)実にソリッドな”合理主義的世界”だ、というのが私の見解なのである(笑)。
(つづく)
”質問”とは?(その2)
| カテゴリー: |
|---|